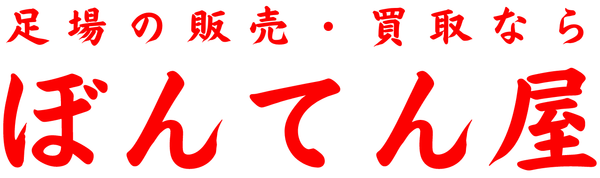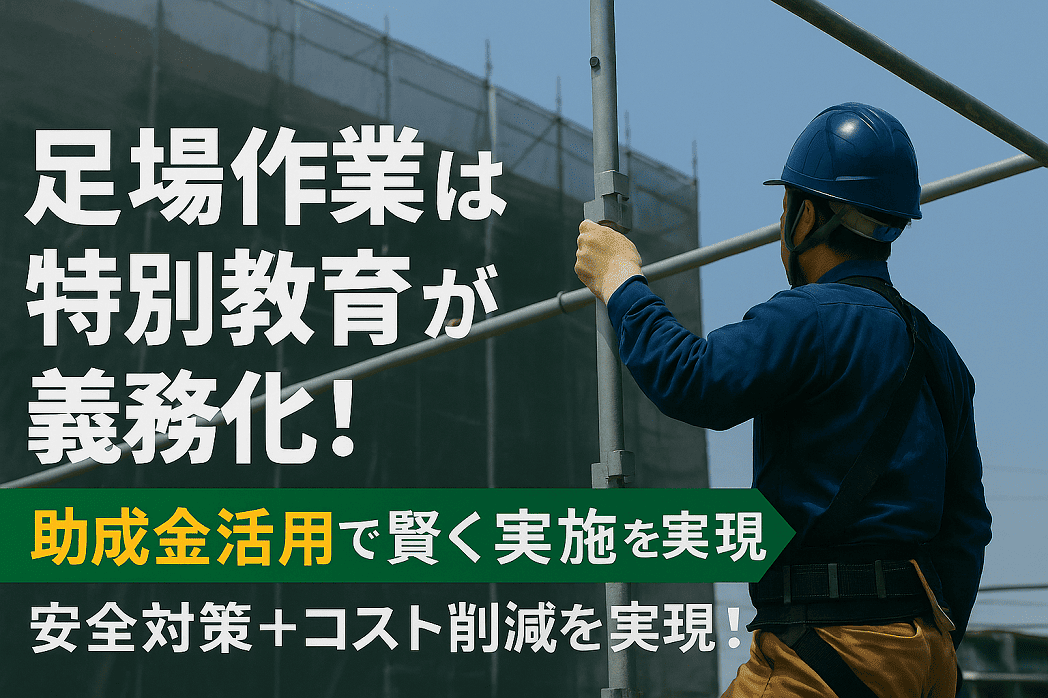
足場の組立て等特別教育はなぜ義務化?助成金活用で賢く実施
足場作業における安全教育の義務化が進み、費用負担や手続きの手間に悩む経営者・現場責任者も多いことでしょう。
本記事では、足場の組立て等特別教育の必要性と講習内容、さらに活用可能な公的助成制度の申請方法をわかりやすく解説します。
助成制度を上手に活用して、安全対策とコスト削減を両立させましょう!
■足場の組立て等特別教育とは?
足場の組立て等特別教育は、足場作業中の墜落・転落事故を防止するために「労働安全衛生規則」により義務付けられた安全講習です。

□受講対象と流れ
1. 受講対象者
- 足場の組立て・解体・変更作業に係る業務を行う者
※2015年7月1日時点に既に従事していた者については短縮コースを選択可能
2. 申込み方法
- 各講習機関(民間の研修センターなど)へ直接申し込む
- 申込時に受講コース(未経験者向け/実務経験者向け)を選択
3. 講習内容
- 以下について学びます。
- 足場及び作業の方法に関する知識
- 工事用設備・器具等に関する知識
- 労働災害防止に関する知識
- 関係法令
4. 修了証の発行
- 講習修了後、修了証が交付され、現場での提示が求められるケースが一般的です。
■なぜ義務化されたのか?背景と狙い
□労働災害の現状
足場作業に起因する墜落・転落事故が多発しており、建設業全体の墜落災害は労働災害全体の約4割を占めていたとの報告があります(厚生労働省資料より)。

□義務化の狙い
- 安全意識の向上:作業者全員が共通の知識を学び、リスクを減少させる
- 災害防止:墜落災害を含む重大災害の防止
- 現場標準化:企業ごとの差異が生じない安全水準の確保
□法改正のポイント(2015年7月1日施行)
2015年7月1日より、労働安全衛生規則が改正され、足場の組立て等作業従事者に特別教育の受講が義務づけられました。
(労働安全衛生法第59条第3項)事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
中小規模事業者でも違反すると50万円以下の罰金(労働安全衛生法第120条)が科されるため、速やかな対応が必須です。
(労働安全衛生法第119条)次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。第五十九条第三項の規定に違反した者
■教育内容と講習費用の実態
□講習時間とコース区分
足場特別教育では、受講者の実務経験の有無に応じて以下の2コースが設けられています。
| コース名 | 対象者 | 講習時間 |
|---|---|---|
| 6時間コース(未経験者向け) | これから足場作業に従事する者(実務経験なし) | 6時間 |
| 3時間コース(実務経験者向け) | 2015年7月1日時点で足場作業に従事していた者(実務経験あり) | 3時間 |
□費用相場と負担イメージ
受講費用の相場は一人当たり約10,000円前後です(2025年5月時点の民間講習機関例より)。
コスト負担がネックになる場合は、後述する助成金を活用して実質費用を抑えましょう。
■助成金のもらい方と申請の手順
足場の組立て等特別教育は、人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)を活用することで、費用負担を大きく軽減できます。以下の手順で申請を行います。
- 対象企業:中小建設事業主(雇用保険適用事業所)
- 対象者:雇用保険に加入している建設労働者(訓練時間の7割以上を受講)
-
助成内容
- 経費助成:中小企業で最大 3/4補助
- 賃金助成:最大 8,550円/人日(規模により異なる)
申請の流れ

-
計画届の提出
訓練実施の3か月前~1週間前までに、所轄の労働局へ提出 -
訓練の実施
認定されたカリキュラムに基づき教育を実施 -
支給申請書の提出
訓練終了後2か月以内に、必要書類とともに申請
※申請漏れや書類不備を防ぐため、記録とスケジュール管理が重要です。
■まとめ
足場の組立て等特別教育は、2015年7月1日から義務化されており、未受講のまま作業を続けると50万円以下の罰金を科されるリスクがあります。
足場の組立て等特別教育は、作業者の知識向上を目的に実施され、未経験者向け6時間コースと経験者向け3時間コースがあります。
講習費用は約1万円程度ですが、公的助成金(人材開発支援助成金)を活用すれば費用負担を大幅に軽減可能。
助成金を賢く活用し、安全対策とコスト削減を両立させましょう!
👉 ぼんてん屋では、自治体や国の補助金を活用するためのサポートも行っています。
申請に必要な資料作成や手続きに関するアドバイスを提供し、初期投資の負担軽減につなげます。